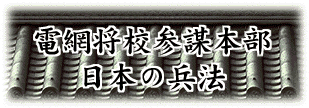|
闘戦経 |
|
兵法書といえば孫子、クラウゼヴィッツというのが大方の相場であろう。あえて日本で、といえば、戦時中の『統帥綱領』、あるいは『甲陽軍鑑』程度しか思い浮かばないかもしれない。甲陽軍艦も兵法を説いたというよりは、武田家の戦略の記録のようなものである。 しかし、日本にも古典的兵法書がないわけではなかった。某氏からの情報提供により、ここに再現することができるのは望外の喜びである。この書の名を『闘戦経』という。 闘戦経は、大江家に伝わるという古書である。作者も、大江維時だとか大江匡房だとか、序に書かれているが、よくわからない。これが応仁の乱での消失をまぬがれ、毛利元就の弟にあたる大江元綱、その家臣の秦出羽守武元を経て、秀吉や家康の時代の大江正豊に伝えられたということらしい。もっとも、こういう古文書はどこまで由緒が正しいかわからないのが相場である。 大江家は代々朝廷に仕えて、文章算道を業としたが、大江家の太祖維時は、第六十代醍醐天皇の延喜元年、勅命によって中国に渡り、六韜・三略・孔明の書など三十巻をもたらしたことが歴史に載っている。また、その子孫の匡房は、後三条天皇に文学で仕え、蔵人から出家して権中納言兼太宰権帥となり、天永二年には中納言を辞して大蔵卿を兼ね、藤原伊房・藤原為房とともに、当時の人から「三房」と呼ばれていた。幼時から神童として知られ、著名な兵学者である。
さて、この闘戦経だが、戦時中には一時「静かなブーム」になったらしい。私の手元に送られてきたのは、昭和19年の研究書である。これ以外にも、海軍などがかなり研究していたらしい。しかし、その後、この書物はすっかり忘れ去られてしまった。 現在、出版物で手に入れるのはほぼ不可能であろう。古書店か、国会図書館(これも古典籍史料室に入ってしまっているらしい)でしか手に入らないはずである。 というようなものが転がり込んでくれば、広く公開したくなるのが私の性分。ということで、どうぞご活用ください。一応、データ化の労力を考慮して、ウェブ上での引用・リンクにあたっては、このURLを明記してくださるとありがたい。 さて、この闘戦経は、歴史的価値、いや、それ以上に戦略書としての価値はどれほどのものであろうか。私にはまだわからない。読者諸賢の感想・研究を待つ次第である。
Special Thanks : ハンドルネーム「大江のちさと」 参考文献:
|
|
石原光将 ISHIHARA Mitsumasa |