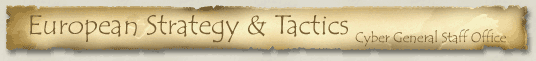 
|
|
|
私が公刊する用兵術の概論は、もともとは皇太子殿下の指導のために書かれたものであり、今までに追加した数多くの補足を考えれば、これはその目的にかなっていると自負している。この書物の真価を認めてもらうために、戦争理論の現在の状態について紙面を割くのが私の義務だと思う。私自身と作品について少々語らなければならないだろう。どうやって思いついたか説明することなく、この理論について私が考えていることや、ここで書いたことの一部を説明することは難しいようなので、どうかご容赦いただきたい。 1807年に出版された原則の章で述べたように、戦争術はどの時代にも存在してきた。特に戦略は、カエサル(シーザー)のものもナポレオンのものも同じなのである。しかし、偉大な指導者の理解に制約され、戦争術は明文化された論文にはまったく存在しなかった。本はどれも、戦術の最も補助的なポイントについて、最も精密(で、言うまでもなく最も未熟)な一般的詳細を含むようなシステムの断片、おそらくは固定ルールに従うことのできるような戦争のごくわずかの部分しか示していない。 現代人の中では、Feuquieres*1、フォラール(Folard:フランスの軍人・戦略家。1669-1752)、Puysegurが資料を作っている。Feuquireresのは非常に興味深く、批判的・教理的な書物だ。フォラールのは、ポリュビオス(Polybius:※古代ギリシアの歴史家。ポエニ戦争に従軍、『歴史』の著者)についての論評と縦陣についての論文である。Puysegurは初の兵站学小論であり、古代の斜行陣についての初の研究だと思う。 しかし、これらの著述者は、彼らが探検したがっていた鉱山にはほとんど深入りしておらず、18世紀半ばの戦争術の状態における概念のみを形作るためにはに、サックス元帥(Saxe:※フランス軍人。フランス軍事史上でも有名な司令官。1696-1750)が著書『夢想』の序で書いたことを読む必要がある。 「戦争は、闇に覆われた科学である。そのまっただ中で、わたしたちは確実な歩みをもって進んでいるわけではない。慣習と先入観、無知からくる自然な結果がその基礎となっている。 「すべての科学には原則があるのに、戦争にだけはない。書物を書いたことのある偉大な指導者も、それを何も残してくれなかった。それを理解するためには学識が深くなければならない。 「グスタフ・アドルフ(※スウェーデン国王。1611〜32)は方法を作ったが、すぐにそこから逸脱した。繰り返しに堕してしまったからだ。慣習以外にはなにもなく、その原則は何も知られていないのである」 これは、フリードリヒ大王が七年戦争中、ホーエンフリートベルク、ゾールなどの戦いで勝利を続けていたころに書かれたものだ。そして、名将サクス元帥は、あまりにも妥当な不満を述べたこれらの暗闇を突破するのではなく、兵士たちに羊毛の軍衣を着せたり、四列横隊(そのうち2隊は槍で武装している)を作るためのシステムを書き上げることに甘んじてしまった。最終的に彼は、「おもちゃの砲(amusettes)」と彼が名付けた小さな野砲の例を提案したが、この名称は、そのユーモラスなイメージにふさわしいものだ。 七年戦争の終わりに、いくつかのよい作品が出現した。大王、偉大なる指導者、偉大なる哲学者、偉大なる歴史家に飽きたらず、フリードリヒ自身が、将兵たちに対する指示によって教訓的な著書まで作ったのである。ギシャール(Guichard)、ティルパーン(Turpin)、メーズロア(Maizeroy)、メニルジュラン(Menil-Durand)は、古代と当代の戦術についての議論を続け、この問題についてのいくつかの興味深い論文を提示した。ティルパーンはモンテククリ(Montecuculi)とウェゲティウス(Vegetius)を批評した。スペイン・サンタクルスのピエモント(Piedmont)のデ・シルヴァ(de Silva)侯も、いくつかの部分でいい議論をした。最後に、デスクルメビーユ(d'Escremeville)が戦争術史の概略を描いたが、これも長所がないわけではなかった。しかし、これらはどれも、フォントノア(Fontenoy)を征服した者が不平を漏らした「闇」を散らすものではなかった。 少し遅れて、グリモア(Grimoard)、ギベール(Guibert)、ロイド(Lloyd)が登場した。最初の二人は、戦闘における戦術と「兵站(la logistique)」*2において進歩をもたらした。ロイドは、興味深い自分の記憶から戦略についての重要な問題を提示した。そこで彼は残念ながら、隊形の戦術について、そして戦争哲学についての緻密な詳細という迷宮に埋没してしまった。しかし、これらを関連づけられたシステムにするという方法で問題を解決することはこの著者にはなかったものの、よい道筋を最初に指し示した者であると言うことを指摘しておくのが適切であろう。とはいえ、二つの作戦だけしか仕上げなかった七年戦争についての彼の記述は、教理的に書かれたものではなく、(少なくとも私にとっては)むしろ教育的なものであった。 ドイツは七年戦争とドイツ革命の間の期間に数々の文書を生み出した。これは多少広範囲に、戦争術の別の第二の分野についてかすかな光で照らし出した。ティールケ(Thielke)とフェシュ(Faesch)はザクセンで出版した。ティールケのは布陣法(castramentation)、野営地と陣地への攻撃についての断章であり、フェシュのは戦争の作戦に附属する部分についての行動原理集である。シャルンホルスト(Scharnhorst)はハノーヴァーで多くのものを書いた。ワルネリー(Warnery)はプロイセンで騎兵についてのかなりよい作品を出版した。ホルツェンドルフ(Holzendorf)男爵は機動戦術について別の著作を書いた。ケフェンフラー(Kevenhuller)伯爵は、野戦と包囲戦についての行動原理を述べた。しかし、これらはどれも、科学の高等分野を満足する概念ではなかった。 Porbeck、Venturini、Bhlowが革命の最初の作戦についての小冊子を出版した19世紀のはじめには、こういうものが戦争術であった。Bhlowは特に、天才的な作品『現代戦闘システムの精神』によってヨーロッパにセンセーションを巻き起こしたが、それは単なる素描にすぎず、ロイドによって示された最初の観念に付け加えるものは何もなかった。同じ頃ドイツで、戦争術の研究に対する入門書という謙虚なタイトルで M. de Laroche-Aymonによって出版された貴重な作品は、戦争術のすべての部門のための実際的な百科辞典であったが、戦略については「ほとんど書くことがない」として除外された。しかし、この省略はあるものの、古典的作品としては最も完全でおすすめできるものの一つである。 ヘルヴェティア(スイス)の大隊長任務を終えたときには、私はまだ最後の二冊に精通していなかった。そこで、18世紀後半の軍事界を揺り動かしたこれらの本を、私は自己啓発のために貪るように読もうとしたのである。プイセギュール(Puysegur)から始めて、メニルジュラン(Menil-Durand)とギベール(Guibert)に至り、戦闘の戦術の多かれ少なかれ完成された「システム」だけしか発見しなかった。それらは嘆かわしいやり方で互いに否定しあっているので、どうしても戦争についての不完全な概念しか与えてくれなかった。 私はそれから、これらの著者のシステムでは私に与えてくれなかった解決を求めるために、偉大な指導者とかかわる戦史についての作品に戻った。フリードリヒ大王の記述は、ロイテン(リッサ)の奇跡的勝利を得させた秘密に私を導き入れ始めていた。私はこの秘密が、敵軍の単一の翼に彼の兵の大半をぶつけるというひじょうに単純な戦術的展開から成っていることに気づいていた。それから登場したロイドの著作は、私のこの信念を強化することになった。それ以後、わたしはまた、ナポレオンのイタリアでの最初の勝利が同じ原因であることを知った。こうして、戦闘にフリードリヒが応用したのと同じこの原則を、戦略を通じて、戦争のチェス盤全体に当てはめるということを思いついたのである(a tout l'echiquier d'une guerre)。私は戦争の科学すべての鍵を握ったのであろう。 この真実については、後にチュレンヌ(Turenne)、モールバラ(Marlborough)、サヴォイ公ウジェーヌ(Eugene)の会戦について読むときにも、フリードリヒ大王との比較においても疑うことができなかった。テンペルホフ(Tempelhoff)は、幾分冗長であまりにも繰り返しが多いけれどもひじょうに興味深い詳述に満ちたフリードリヒ大王の本を出版したところだった。わたしがそこで理解したのは、サックス元帥が1750年に述べた「戦争術について確立された原則は存在しない」ということはまさに正しいにもかかわらず、その多くの読者は、元帥の序文をもって「これらの原則は存在しない」と考えたものだ、と解釈したのはひじょうにまずいことだった、ということだ。 真実の法則を発見するために戦争の理論を考えるべきであり、また我流のシステムというあやしげな立脚点から常に離れることが必要であるという正しい観点をつかんだのだと確信して、わたしはneophyteの全熱情を傾けて仕事に没頭したのである。 1803年の教科書の中で、在パリ・ロシア公使 M.d'Oubril にまず最初に提出し、それからネイ(Ney)提督に提出した一巻を書いた。しかし、その後私の手に入った Bhlowの戦略に関する作品と、Roux-Fazillacによって翻訳されたLloydの歴史的物語のために、私は別の計画を行なうことに決めた。私の最初のエッセイは、戦闘命令、戦略的行軍、作戦戦線についての教訓的論文であった。それはその性質上無味乾燥で、種類ごとに分類されたために相互参照に不便な歴史の引用があまりにも散在していた。同じ章のなかで、1世紀単位で事件が分割されることも多かった。ロイドが特に私に納得させたのは、、戦争全体についての批判的・論争的な話は、行動原理を並べ立てるのではなく、物語の中と事件の中で関係と統一を保つほうがよいということであった。というのも、10の会戦の1シリーズで、戦争についてありとあらゆる行動原理を当てはめて提示するのに充分だからである。それから私は最初の作品に熱中し、ロイドが完成しなかった七年戦争の続きを書くプロジェクトを再開した。このモードは私に適していた。私は24歳でしかなく、わずかな経験しかなかったのに、多くの既成概念を攻撃して大いなる名望を幾分侵害しつつあったので、彼ら自身に語らせるような出来事への強力な支援が私にに必要だったからである。そして私は、あらゆる種類の読者にさらによりふさわしいものとして登場したこの最後の計画を決定した。確かに、公的教科書のためにも、これらの会戦の詳述において多少散漫な科学の組合わせの総体を回想するためにも、教訓的な論文の方が望ましかったであろう。しかし、私自身は、論じられている会戦について注意深く読むほうが、教条主義的な書物をすべて一緒に読むよりもずっと多くの利益を得たと白状する。そして、私の1805年に出版された本は、学生ではなく上級将校のために書かれていた。同年勃発したオーストリアとの戦争のために、著書に対して必要な力をすべて動員することができず、わたしが実行できたのはプロジェクトの一部分にすぎなかった。 それから数年後、大公[オーストリアのカール]が地上戦闘についてのフォリオ版のすぐれた作品への序文をしたためた。ここに彼の天才的素質が示されていた。ほぼ同じころ、当時オーストリアに従軍していたヴァーグナー少佐(Wagner)による戦略についての小パンフレットが登場した。このエッセイは賢明な視野に満ちており、その著者がいつかもっと完全なものを仕上げるだろうと確信させるものであって、それは最近実現した。プロイセンでは、シャルンホルスト(Scharnhorst)将軍が成功に関するこれらの疑問を打診し始めた。 そしてついに、地上戦に関する私の最初の論文から10年後、カール大公の重要な作品が登場した。それは教訓と歴史の二つを統合したものだった。この公子は最初に短く戦略的行動原理を示し、それから実際的適用を行うたのに1796年と1799年の戦役に対する批判的歴史を4巻で示した。戦いぶり以上に秀逸な公子の名声を高めたこの作品は、戦略科学の基礎を完成させるものだった。この戦略科学は、ロイドやブロウが最初にベールを取り払い、私が1805年に作戦戦線についての章で第一原則として示し、1807年にSilesiaのGlogauが自費出版した戦争術の原則の基礎についての章でも示したものである。 ナポレオンの凋落は、多くの研究官僚を平時の閑職にまわすことによって、あらゆる種類の大量の軍事文書が現われるきっかけとなった。Rogniat将軍は軍団あるいは共和制部門のシステムに戻すことを望み、ナポレオンの冒険的システムを攻撃したことで、議論を呼んだ。ドイツには特に教条的な作品が多かった。バイエルンのXilander、ウィッテンベルクのTheobaldとMuller、プロイセンのワグナー、Decker、Hoyer、Valintiniらは、さまざまな本を出版したが、それはカール大公と私の行動原理の反復と、その適用における発展でしかなかった。 これらの著者の中には、現実の勝利よりも巧妙に、作戦の中央線についての私の記述と争う者もおり、ときにはあまりにも厳密すぎる計算をする者もいたが、私たちはそれらの書物が優れたものであるという推薦文を書くことを拒否できなかった。多かれ少なかれ優れた見解を含んでいるからである。 ロシアでは、Okounief将軍が三軍の統合と部分的活用についての重要な記事をしたためた。これは戦闘理論の基礎を示すものであり、それゆえに現実の任務を若い将校に示すものであった。 フランスでは、Gay-Vernon、Jacquinot de Presle、Roquancourt が、メリットのなくはない教科書を出版した。 このことで、何人かの書き手がひどい理解をしてきた、作戦戦線についての私の章の原則について防衛するという利点があった。そしてこの論争によって、少なくとも多少は理性的な定義がもたらされ、同時に中央作戦の現実の利点が主張された。 この分析的な一覧の発表から一年後、ドイツのクラウゼヴィッツ将軍が亡くなり、未完の概略として書き残された著作を死後出版するよう未亡人は託された。この作品はドイツに大いなるセンセーションを巻き起こした。私としては、著者が私の『戦争術の概論』を精読して、その真髄を反映させることなく書かれたことを残念に思う。 クラウゼヴィッツ将軍の大いなる学識と達者な筆を否定することはだれにもできない。しかしときどき少々気まぐれなこの筆は、単純明快が最も必要な教訓的な議論には少々もったいぶりすぎている。それは別にしても、著者自身があまりにも軍事科学の点においてあまりにも懐疑的すぎる。その第一巻は戦争理論すべてに反論する熱弁でしかないのに対して、二巻・三巻は理論的な行動原理に満ちており、著者が他人の教義は信じなくても自分自身の教義の効果については信じていたということを証明している。 私自身は、この博学の迷宮中にきらりと光るアイデアや顕著な記事はごくわずかしか認めることができなかった。そして著者の懐疑主義には共感するものは何もなく、よい理論として必要性や有用性も彼の著述から感じることはありえなかった。たとえそのように頼まれたとしても。無知よりも悪い知ったかぶりに陥らないようにするため、評価されるべき限界について合意することはまさに重要だ*3。「原則の理論」と「システムの理論」のあいだにある違いを区別することが、特に必要である。 この概論の文章のほとんどの部分で、彼らの扱っている多様な主題に対して与えられる絶対的な規則はほとんどない、と私自身が認めていることは、おそらく反論されるであろう。この真実に対して絶対の確信はあるが、それは「理論がまったくない」ということなのだろうか? もし45の記事中、あるものは10のまともな行動原理を有し、他のものは1つか2つであるとして、戦略的・戦術的教義の立派な総体を形成するのに150から200の規則があれば充分ではないのだろうか? そして、そこにあなたが多少の例外のあるような多くの指針をあなったが追加したとして、戦争の作戦すべてについてのあなたの主張を固定させるだけにしか役立たない教義しか持っていないということになるのだろうか? 私は、この概論の中で、特別軍に関する特殊な書物ではなく、一般論のみに言及した。Montalembert、BousmardのSaint-Paul、Carnot、Aster、Blessonらの著書は、包囲攻撃と築城法について進歩をもたらした。Laroche-Aymon、Muller、Bismarkは騎兵問題にある多くの問題点を照らし出した。あいにく、発行後6年間知ることのなかった雑誌で、ビスマルクは私とその作品を非難することを義務と信じている。なぜなら、私は著名な将軍の信念について、「プロイセン人は、彼の最新のパンフレットに騎兵将軍に対する未完の政府命令があるのを見てから、彼をとがめてきた」と述べたことがあるからだ。私の作品を非難するにあたって、ビスマルク将軍は、報復行為に対して要求するという理由だけでなく、すべての本が裁かれて議論されるという理由をもって、自らの権利を濫用してきた。その間、非難に答えたり、単なる不平を漏らしたりするのではなく、彼は誹謗中傷によって報復するのがたやすいと考えた。軍人は本では報復するのではなく、有名人を集める以外の目標を持つべきだというのだ。B________ 将軍が私に帰している滑稽な話に関心を示している人々なら、どちらが正しいか判断してくれるだろう。 私が1807年に出版して、軍事界で一定の認識を得ている「原則」の章で、「私以前には戦争術が存在しなかった」などと私が言ったというような告発があるが、この最初のフレーズはこの言葉で始まる。「戦争術は大昔から存在した」。私が言ったことは一般原則の存在について述べ、あるいは戦場のすべての結合に至る戦略を通してそれを適用させた本がなかったということである。それは私が最初に示したのであり、私から10年後でも他の人は改善していないし、完成した人もいない。この真実を否定する人は素直ではない。 残りについては、私は自ら科学に没頭する個人的学究の徒を攻撃して私の筆を汚したことはない。そして、もし彼らの教義との共有点がなかったならば、もっと適切で公平に表現してきたことだろう。そうであればよかった。さて、本題に戻ろう。 砲術は、Gribeauval と d'Urtubie が備忘録を書いてから、大量の文章がある。その大半は、Decker、Paixhans、Dedon、Hoyer、Ravichio、Bouvroyらだ。その他、de Chambray 侯爵と、歩兵の火力についてのOkounieff将軍の著書に議論がある。最後に、ウィーン、ベルリン、ミュンヘン、シュトゥットガルト、パリの興味深い軍事雑誌に掲載された士官軍(host of officer)についての学術論文は、彼らが議論した部門の継続的発展に寄与してきた。 いくつかのエッセイが、古代から現代に至る兵法史を試みた。Tranchant Laverne は熱心に、また賢明に行なったが、完成していない。Cario
Nisasは、古代にあまりにも紙幅を割きすぎ、ルネッサンスから七年戦争の時代については平凡で、現代のシステムについては完全に失敗している。Roquancourt
は同じ主題をもっとうまく扱った。プロイセンのCiriaci少佐とその後継者はもっとよくやった。最後にナポリ将校blanch大尉は、書物に書かれたものと現実のものとしての戦争術のさまざまな時代について興味深い分析を行なった。 その一方で、理論をできるだけ完全にするために、重要な仕事がまだ残っていることを認めなければならない。見たとおり、それは長い間なされてこなかった。それは、過去一世紀の間続いている四種類の異なったシステムの完全に深い調査である。七年戦争、フランス革命の最初の諸会戦、ナポレオンの大侵略、ウェリントン、それぞれのシステムだ。この調査から、通常の戦争にふさわしい、混合したシステムを推論することが必要である。それはフリードリヒとナポレオンのとった方法とも関わっている。いや、もっと適切にいえば、軍事力対軍事力の通常の戦争のための、そして大侵略のための二重システムを開発することが必要だということだ。この重要な働きについては、3章24項で概論した。しかし、この主題は一冊分の内容があるので、その任務は、完成させようという気力と時間を持つ人か、テストとして自ら新しい試みにおいてこの混合教義を試してみるという幸運な人に示唆するにとどめておきたい。 さて、この解説と私の最初の論文がテーマとなっていた論争についての信念を宣言することで、この簡単な概略を終わらせるとしよう。最近30年間の科学のおそるべき発展と、M・クラウゼヴィッツの猜疑心とを比較して出てくる賛否の議論をすべて天秤にかけて、私の原則と、そこから引き出される実行原理が、ある著述者たちからひどく誤解されていると信じている。完全に誤って解釈している者もいれば、私の頭から出てくるはずもないような誇張された結論を引き出している者もいる。数十の会戦を率いてきた将校ならば知っているはずのことだが、戦争というのは壮大なドラマであり、そこでは数千の物理的・精神的要因が多かれ少なかれ強力に働き、それは数学的計算では導き出せないのである。 しかし、私は率直に言って、20年間の経験で、私は以下の信念を強めるだけだったということを認めることもできる。 「逸脱すれば必ず危険であり、逆にそれを適用することはほとんどいつでも成功の栄冠をもたらすような戦争の基本原則がごく少数存在する」 「これらの原則から引き出される適用法についての行動原理もまた数は少ない。ときには臨機応変に適用させられるが、それでも、騒然たる戦闘のまっただ中での大作戦を実施するという、常に困難で複雑な任務を遂行するために、軍司令官にとっての羅針盤として一般的に役に立つものである」 「戦争術に関するすべての理論のなかで、唯一妥当なものは、戦史研究に基づき、諸原則を調節して一定数に収めている。それでも生来の天才は、排他的規則で拘束されることなく、戦争の一般的指揮において重要な部分担うものである」 「反対に、戦争は明確な(positive)科学であって、そのすべての作戦は間違いのない計算に置き換えられるという誤った考え方に基づく知ったかぶりの理論以上に、生来の天才を殺し、勝利に対して過失を発生させるものはない」 このように公言した後も、確定した歯車仕掛けのメカニズムをこの技術から作ることを望んでいるだとか、あるいは逆に、あたかも原則の一章を読むだけで瞬時にして軍を指揮する才能を手に入れられるかのように述べている、などととして非難されたくないと思っている。人生のあらゆる状況におけると同様、すべての技術において、知識とM能力は二つの完全に異なったものである。そして、能力だけによってしばしば成功する人がいたとすれば、さらに二つを統合させることで一層すぐれた人となり、完全な成功を保証することになるのである。同時に、しゃくし定規な理由で非難されないようにあらかじめ断っておくが、知識といったとき、私は博学であることを指して言っているわけではない。多く知ることではなく、よく知ることが問題なのである。特に、我々が命じられている任務に何が関連するかを知ることが。 これらの真実をよく理解している読者の皆さんには、この新しい概説をよろしくご笑納いただきたい。これは今や、王子または政治家の指導に最適の書として提供されていると信じるものである。 私はここまでの記述で、我々の時代を際立たせてきた軍事史の作品について言及することは、自分の義務と考えなかった。なぜなら、私が扱うべき主題に実際に関係してこないからである。しかし、我々の時代の人たちが科学の進歩に貢献してきたのと同じように、成功の原因を説明するために、彼らについて二、三語っておいてもいいだろう。 純粋な軍事史は感謝されず、難しいものである。というのも、その技術を有する人々にとって有用であるという観点からいえば、詳細においては素っ気ない記述より詳細なほうが必要とされるのだが、場所と動きを記載するためには正確な判断が必要とされるからである。そのため、ロイド(Lloyd)の書いた七年戦争についての不完全な概略に至るまで、軍事評論家たちは誰も、公式な記述か、多かれ少なかれうんざりするようなお世辞から逃れることができていないのだ。 第一級の18世紀の軍事史家といえば、デュモン(Dumont)、クインシー(Quincy)、Bourcet、Pezay、Grimoard、Retzow、Tempelhoffである。最後の人物は特に学派のようなものをなしているけれども、彼の作品は行進と野営の細部に少々過剰にこだわりすぎている。戦場の描写は疑いもなくよいものであるが、戦争全体の歴史についてはまるで役に立たない。というのも、ほとんど毎日同じ形式で述べているからである。 ドイツにおけると同様フランスでも、1792年から大量に作品が登場した純粋戦史は、名前を記すだけでも一冊のパンフレットになるほどである。というわけで、ここではグリモア(Grimoard)の最初の革命戦争、Gravert将軍の作品、シュシェ(Suchet)やサンシール(Saint-Cyr)の自伝、Gourgaudの断章、Montholonの断章、Beauvais将軍の指揮による勝利と征服についての大作、ヴァーグナー大佐による戦闘の広範な収集、同じくKaussler少佐によるもの、Napierによるスペイン戦争、Reynierによるエジプトのもの、LaverneによるSuvaroff作戦、Stutterheinによる部分的な記述、同じくLabaumeによるものを指摘するにとどめておきたい。*4 政治的でもあり軍事的でもある歴史はもっと多くあるが、さらに扱いが難しく、また教訓的な内容とは安易に結びつけられない。というのは、その記述を壊さないように、軍事的記述の要点となるような細部を隠してしまうからである。 ナポレオンの没落まで、政治軍事的歴史は数世紀に渡って唯一の作品しか注目に値するものがなかった。それはフリードリッヒ大王の『我が治世の歴史』である*5。優雅なスタイルと歴史・政治についての広範な知識を要求するこの種のものは、出来事を正確に判定するに充分な軍事的な天賦の才能を必要とする。このような傑作を作り出すには、Ancillonのように国家の関係や利害を描写したり、ナポレオンやフリードリヒのような人物が戦闘を振り返る必要がある。彼の作品のような傑作を探すとすれば、ここ30年間によい作品がいくつか登場している。この中には、Foyによるスペイン戦争、Mathieu H. Dumasによる軍事的な出来事の概説、Fainの原稿などがある。この二つ目の作品は確固とした視点を欠いており、3つ目はあまりに多くの偏見があるけれども。それから、M. Segur弟の作品がある。この著者は才能に溢れていて賢明な視点を持っており、彼の書いたチャールズ8世の歴史では、もう少し文体において能力があったならば、黄金時代のギリシアの歴史家ポリュビオス以来の歴史家となっていたであろうことを証明した。第3ランクとして、我々はToulongeonやServanの歴史をもってくることにしよう*6。 最後に第3の種類として、技術の原則に当てはめられて、それらの原則と出来事の関係を示すことを特に主眼に置いた批判的歴史書がある。FeuquiPresとLloydはその先駆であるが、革命までの間はそれほど多くの模倣者がいたわけではない。最後の種類は、この携帯ではあまりはっきりしないけれども、おそらくその結果については有益であるというだけであろう。特に批評は厳密さに欠けるため、誤った不公平なものに成り下がりがちである。 過去20年間に、この半ば教訓的、半ば批判的な歴史は他のものより大きく発展を遂げた。いや、少なくともいいものになるよう洗練されてきた。そして、論争の余地のない成果を作り出した。カール大公によって出版されたキャンペーン、Muffling将軍による無名の作品、Pelet将軍、Boutourlin、クラウゼヴィッツ*7、Okounieff、Valentini、Ruhleの関係部分、Messrs、de
Laborde、Koch、de Chambrai、Napierの作品。それから最後に、ベルリンとウィーンの興味深い学術雑誌にMessrs、ヴァーグナ、Scheelによって発表された断章は、戦争の科学の発展に多かれ少なかれ支援した。おそらく私は革命戦争についての長い批判的軍事史その他私の出版した歴史作品が、この成果に部分的に寄与していると述べてもいいと思う。革命戦争についての私の長い批判的軍事史その他の私が出版した歴史的作品がこの成果に少々寄与していると述べてもかまわないであろう。というのは、原則の適用についての恒久的勝利を証明するように書かれたこれらの作品は、この支配的な視点に対してすべての事実を提示することに成功しているのであり、少なくともこの点に関して、彼らは幾分受け継いでいる。この主張を証明するものとして、Dumesnil大尉によるスペイン継承戦争のスパイスの利いた批判的分析を例示しておきたい。 |
| 石原光将/ISHIHARA Mitsumasa |